|
所得税では、上場株式等から受け取る配当金は配当所得、上場株式等を譲渡等したことによる利益は、分離課税の譲渡所得に区分されます。投資信託の税制については少し複雑だったのですが、ようやく少し理解しやすいものになりました。
とりあえず、譲渡等をした場合の税率からお話ししていきますね。上場株式や株式投資信託を譲渡等することによって得た収益には、分離課税の譲渡所得となり、復興特別所得税を除くと、20%(所得税15%、住民税5% 復興特別所得税込 20.315%)の税率が課せられることになっています。平成26年より税率が変更されていますから注意してくださいね。
以前は、株式投資信託の譲渡・解約に関する税制は、換金方法によって、所得区分が異なっていてちょっと複雑だったのですが、現在は、いずれの換金方法によっても株式と同じく分離課税の譲渡所得として扱われることになっています。
へぇ〜・・・で終わらせてはいけませんよ!!!
所得区分が同じになっているということは、
 所得内の通算=内部通算(同一所得内で損と得を差し引きすること)ができる!!! 所得内の通算=内部通算(同一所得内で損と得を差し引きすること)ができる!!!
ということですよ。現在は、株式投資信託を解約請求によって換金した場合でも、買い取り請求によって換金した場合でも、株式を譲渡したことによる利益・損失との通算が可能になっているのです。
さ・ら・に!
株式・株式投資信託の売却等によって発生した損失と株式・株式投資信託から分配金・配当を受け取ることによって得た利益を通算することもできるようになっています。
これは、所得区分が以下のように異なりますから、
株式・株式投資信託の売却等によって発生した損失 → 分離課税の譲渡所得
株式投資信託から受け取る分配金・配当金 → 配当所得
この通算は、損益通算(=所得の壁を越えた損益の通算)との呼び名にかわります。ただ、この損益通算は、分離課税を選択した場合の配当所得に限定されており、給与所得等の他の所得と通算できる不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の一般的にいうところの損益通算とは、手順が異なりますから、わけて覚えておいたほうが良いかもしれませんね。
また、平成21年までは、配当所得との損益通算は、確定申告をおこない申告分離課税の配当所得を選択した場合に限られていましたが、平成22年分以降は、特定口座(源泉徴収ありを選択した場合)に上場株式等の配当・公募株式投資信託の収益分配金を受け入れることが可能となり、特定口座内での通算が可能となっています。
ただし!!!配当所得について、この損益通算をおこなうためには、分離課税の配当所得である必要があり、総合課税の配当所得を選択した場合は、この損益通算ができない点には、変わりありません。改正が続いていますから、わかりにくい面もあるかもしれませんが、

分離課税の配当所得を選択 → 株式等の譲渡所得との損益通算可能、配当控除×
総合課税の配当所得を選択 → 配当控除の適用可能、損益通算×
※注 J−REITから受け取る分配金については、配当控除の適用はありません。
というように、きちんと整理して覚えておくようにしましょう。
では、次に分配金に関する税務について説明します。 株式投資信託の分配金は配当所得に分類されます。
税率は、
株式投信の分配金→配当所得→20%(所得税15%、住民税5% 復興特別所得税込 20.315%)
となっています。公社債投資信託の税制については税率は20%ですが、平成28年より下記の改正がなされています。債券にかかる税制の改正とあわせてチェックしておくようにしましょう。
※ 参考 復興特別所得税
平成25〜平成49年までは、上場株式等の譲渡益や配当等の所得税額に対して、2.1%を乗じて計算した復興特別所得税が上乗せして課税されます。
株式等の譲渡、配当金等にかかる税率 20.147%(所得税15.315%、住民税5%)
計算式 → 15%+15×2.1%= 15.315%
また、株式投資信託から受け取る分配金のうち、投資元本の払い戻しに該当する特別分配金(元本払戻金)には税金はかかりません。これについては、以下の図をみてください。
● 特別分配金(元本払戻金)とは?
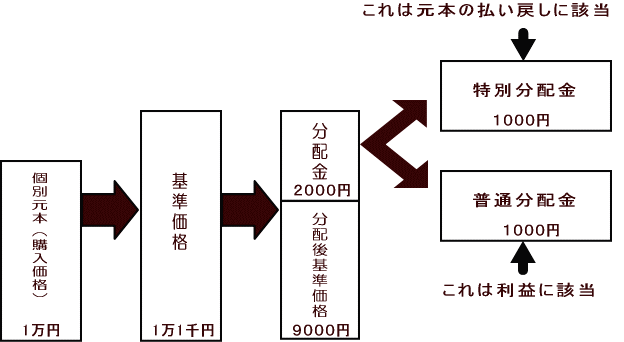
この図では、10000円で購入した投資信託の価格が11000円まで上昇したところで、2000円の分配金が支払われ、分配後の元本は9000円となったことを表しています。
ということは、分配金2000円の内訳は1000円は利益、1000円は元本の払い戻しということですから、本当の利益は1000円部分だけですね。

ですから、利益となっているほうの1000円は、普通分配金として課税対象となり、元本の払い戻しに該当する部分の1000円、特別分配金(元本払戻金)には課税されないということになります。
※注 ETFから受け取る分配金には、特別分配金(元本払戻金)は存在しません。上場株式から受け取る配当金と同様の扱いとなります。
※ 特別分配金は、元本払戻金という名称に変更されましたが、混乱を防ぐため、現在は両方の名称が使用されています。
したがって!!!
この場合の税引き後の受け取り分配金の額は、
普通分配金 → 20%(復興特別所得税を除く)の税金が引かれる = 1000円 − (1000円×20%) = 800円が手取り額
特別分配金(元本払戻金) → 課税なし = 1000円そのままが手取り額
 税引き後の受け取り分配金の額 = 800円+1000円 = 1800円 税引き後の受け取り分配金の額 = 800円+1000円 = 1800円
となります。分配金に対する税制については、FP試験において、非常によく出題される箇所のひとつです。特別分配金とは、なんなのか?税引き後の受け取り分配金の額はいくらとなるのか?このあたりの質問に解答できるようになるまで、しっかり学習しておくようにしましょう。
☆ 平成28年1月1日以降の証券税制 主な改正点
平成28年1月より、債券や公社債投信の税制が変更され、特定公社債については株式や株式投信の税制とほぼ同一となります。
特定公社債とは・・・国債、外国国債、地方債、外国地方債、公募公社債、公募公社債投資信託(MRF、外貨建てMMF等)など
一般公社債・・・私募公社債投資信託など
◎ 特定公社債に該当する債券の税制
| |
2015年まで |
2016年以降 |
| 利付債券の譲渡益 |
非課税 |
譲渡所得 申告分離課税 |
| 利付債券の利子 |
源泉分離課税 |
利子所得 申告分離課税 |
| 利付債券の償還差益 |
雑所得 |
譲渡所得 申告分離課税 |
| 割引債の償還差益 |
発行時に源泉分離課税 |
譲渡所得 申告分離課税※ |
※ 平成27年12月31日以前に発行された割引債は従来通り源泉分離課税の扱いのままとなります。
・特定公社債の税制が利子所得および譲渡所得の申告分離課税へと変更されたことにより、平成28年1月以降は、これらの所得を上場株式等の配当所得および譲渡所得との損益通算や3年間の繰り越し控除の対象とすることができるようになります。
・平成28年1月以降は、特定公社債を特定口座に受け入れることが可能となります。特定口座 源泉ありを選択している場合は、特定公社債等の利子も受け入れることができます。
※ 平成28年1月の段階では特定公社債はNISA口座(非課税口座)の受け入れ対象にはなっていません。
  


|
本ページには、FP技能士受験生が良い結果を得られるように、無料FP技能士ポイント講座をはじめとする様々な無料コンテンツが含まれています。受験生の方が、これらの無料コンテンツを利用してFP技能士試験の学習をしていただくことは、もちろんかまいませんが、無断転載、無断複製等については、かたくお断りいたします。
Copyright(c)2007年−2017年 1級ファイナンシャルプランニング技能士 星野直輝 All Rights
Reserved
|
| ![]()
